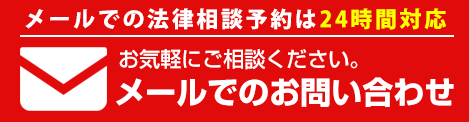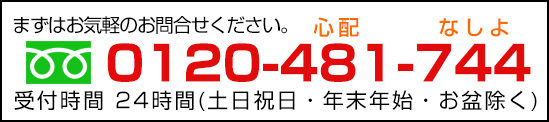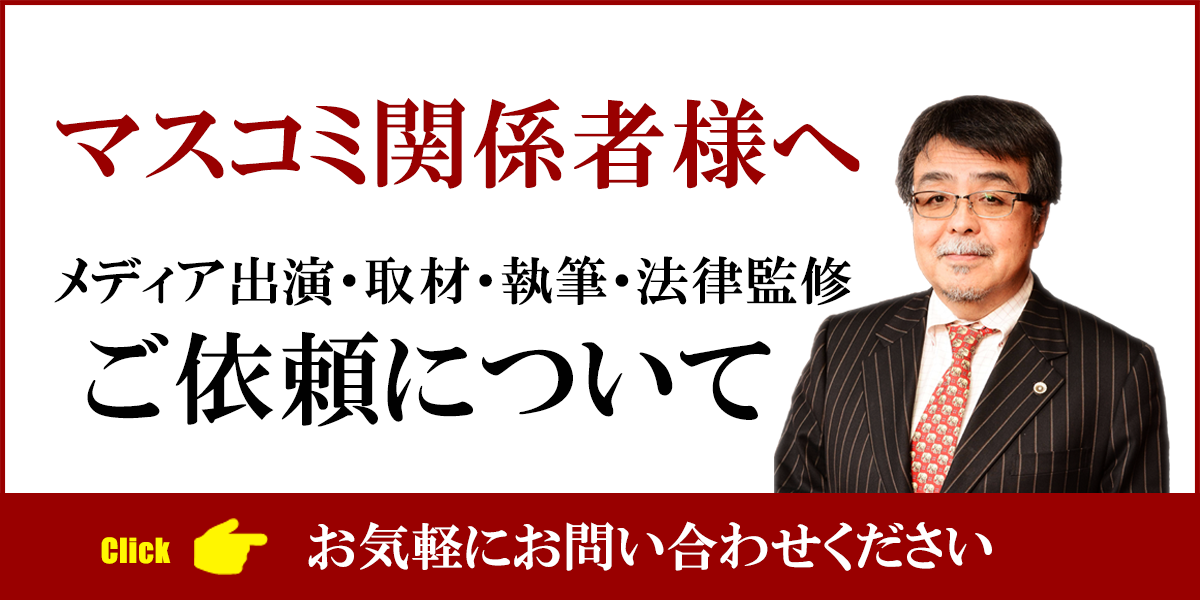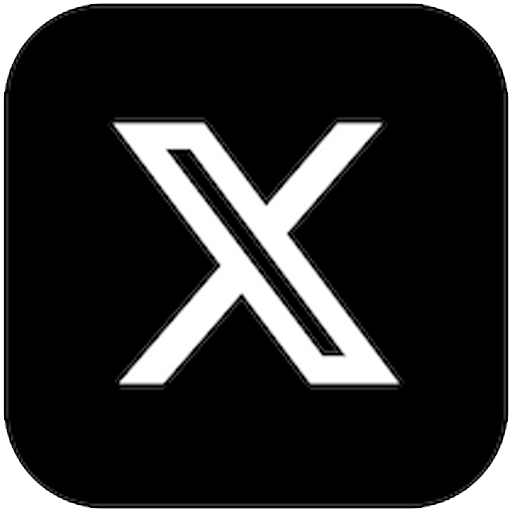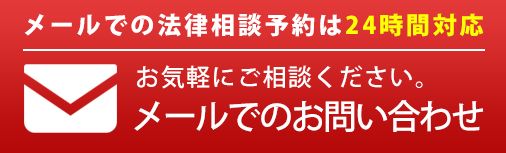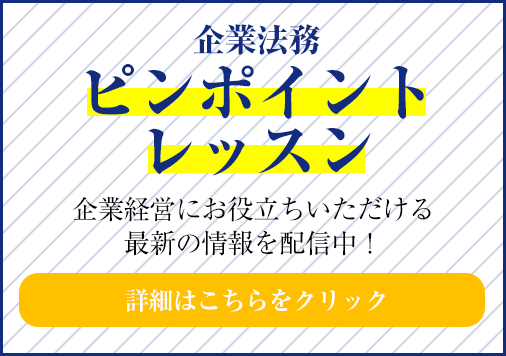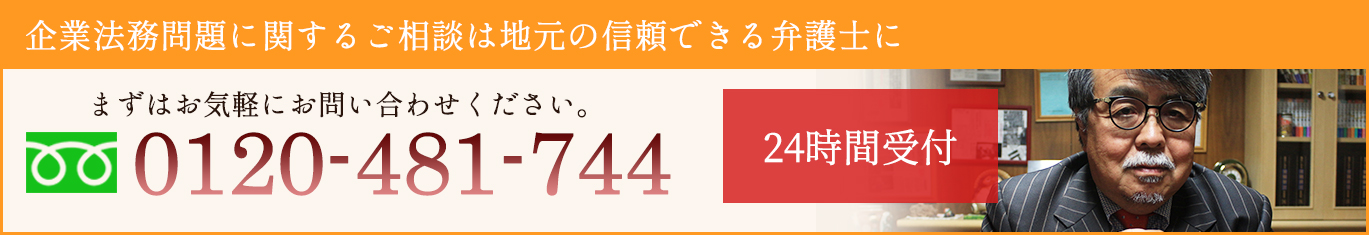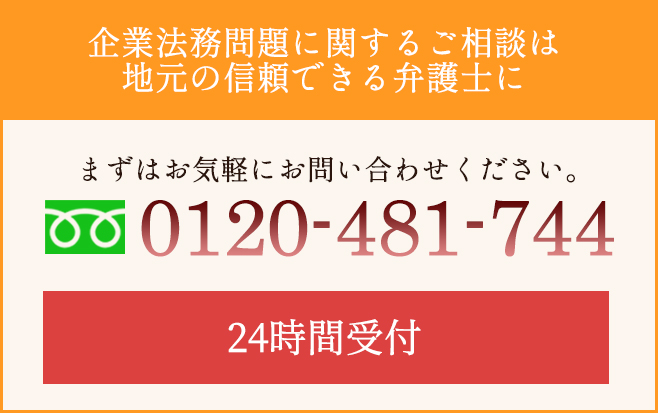Contents
裁判実務の「常識」を覆す:【オーナー社長の死亡事例】なぜ賠償額が1.5倍に跳ね上がったのか?
事案の特殊性を明らかにし、裁判実務上の取扱いの例外として扱われるべき事例であることを説得すること:オーナー社長の死亡に対する対処の事例
会社の代表取締役の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例
札幌地方裁判所平成9年1月10日判決
判例タイムズ」990号228号
本件は、交通事故で死亡した会社の代表取締役である被害者の遺族らが、損害賠償を請求した事案です。
被告の保険会社が訴訟提起前に最終的に提示した金額が5927万8720円でした。
そして、訴訟提起後、担当裁判官が和解案として提示した金額は、6653万0848円でした。
しかし、判決で認容された金額は、8158万5280円であり、遅延損害金も含め最終的に獲得した金額は9202万9710円となりました。
本件では、死亡による「逸失利益」(死亡した被害者が将来得られるはずであった利益)算定の基礎となる報酬の範囲も争点となりました。
交通損害賠償訴訟においては、大量の同種事案を公平・迅速に処理する必要から、基準化が図られ、争点に関する裁判所及び当事者の認識が相当程度共通化されています。その場合、「逸失利益」の算定は、実際には得ることができなかった損害ですから、「虚構・フィクション」の強いものとならざるを得ません。
基準化された内容は、「裁判実務上の取扱い」などもと呼ばれ、「評価基準」とその「判断資料」が語られます
会社役員の逸失利益について、特に小規模会社の場合には、役員の報酬の中に実質的には利益配当部分が含まれることがあるところから、逸失利益の算定の基礎収入からその分を控除し、労務対価部分のみ逸失利益として認容すべきとされています(「評価基準」)。
そして、実際上、どの程度を労務の対価とするかの判断は著しく困難であり、会社の業績、稼働状況、報酬額、他の役員の年収等を総合考慮して個別具体的に判断することになるとされています(「判断資料」)。
その具体的な金額については、名目的な報酬額の何割といった形で認定する手法が採られることも多く、実際は、判断資料の検討は形式的で、ざっくりと機械的に一定額を控除しているきらいがあります。
機械的に「実務的取扱い」に従って判断されると、不利益な結果となるという局面があります。その場合、弁護士としては、依頼者の立場で、「実務的取扱い」が形成された背景を見定め、裁判官には、事案の特殊性を具体的に理解させ、例外として扱うよう裁判官を説得することに注力しなければなりません。
担当裁判官は、一定割合を控除するのが当然というスタンスで和解案を提示してきましたが、当方は、実務上の取扱いがされる背景を詳細に論じることに加え、中小企業社長の年収総額の実態調査が掲載されている資料を証拠として提出するなどして、端的に、死亡した会社代表者の実収入がいかに低額なものであったかを明らかにしました。
本判決は、Aの利益配当部分は逸失利益の基礎となる収入から除外すべきであるとする主張については、Aの稼働状況及び年収、他の役員の年収との対比、代表取締役に就任していたB社とC社の業績等に照らすと、死亡当時得ていた収入は、すべてAの労務の対価であると評価するのが相当であるとして排斥しましたが、その具体的な根拠とか、詳細な根拠は説示されていません。
しかし、審理過程に照らすと、裁判官が、死亡した会社代表者の役員報酬が、安すぎるとことを認識したことに尽きるのです。
前田尚一法律事務所の取組
私は、依頼者にとっての「勝利」とは何かにこだわっています。
また、紛争解決のモデルは「訴訟」であり、実際に「訴訟」を行うスキルとマインドが、弁護士に必要な基本的な能力だと考えています。
これまで、さまざまな訴訟に取り組みながら、中小企業の「企業法務」全般に注力し、常に30社以上の企業を顧問弁護士として直接担当し、30年以上の弁護士としての経験と実績を積んできました。
この経験と実績を活かし、依頼先企業の実態や事情に加えて、企業独自の志向や経営者のキャラクターやパーソナリティも考慮し、紛争の予防と解決に取り組んでいます。
ご興味があれば、お気軽にご相談ください。
[ご参考]
Contents [hide]
- 1 企業間紛争について民事訴訟の活用場面:特に中小企業の場合を念頭に
- 2 企業間紛争を民事訴訟で解決するメリットとデメリット
- 3 民事訴訟で「勝つ」ために
- 4 当事務所の取扱事例からエピソードをいくつか
- (1)事案の特殊性を明らかにし、裁判実務上の取扱いの例外として扱われるべき事例であることを説得すること:オーナー社長の死亡に対する対処の事例
- (2)躊躇する裁判官の背中を押す:土地区画整理事業の事例
- (3)裁判官の判断は、その個人的な視野・価値観の外にはでない(勝訴判決が判例雑誌に掲載される前に、逆転判決が出て狼狽えたこと):ゴルフ会員契約の解除の事例
- (4)裁判官が判決の理由を書きやすい主張を構成する:会社の支配権の確保の事例
- (5)事件ごとにそのたび、そのたび繰り返さなければならない:オーナー社長の死亡に対する対処、再び
- (6)裁判例の相場どおりにせずに、認容額を増額させたり[原告事案]、割合を下げて支払額を減額する[被告事案]:名誉毀損の事例、商品取引の事例、官製談合の事例
- 5 弁護士の選び方
- 6 前田尚一法律事務所の取組