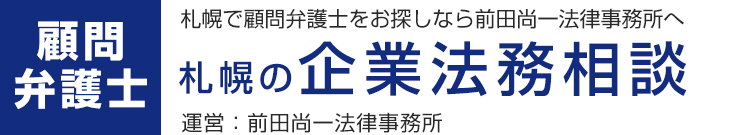

事業の性質や業態に応じて繰り返す特定の特殊業務について迅速に対応してもらいたいと考えている企業は、専門に特化した弁護士を継続的に活用していることが多いです。
しかし、そうでなくとも、経営者は、さまざまな法的な観点での検討が必要そうなトラブルや課題に、それも、突然に直面します。
・ふと不安や悩みが脳裏をよぎったら、法律問題であるかどうかはともあれ、すぐに弁護士と相談したい
・やりとりは、きちんとコミュニケーションがとれる弁護士としたい
・弁護士の説明によって、自分の置かれている立場を客観的かつ具体的に理解し、適切な解決方法を見つけることができる体制を作っておきたい
・必要な専門性のある弁護士の意見が欲しい
・「勝ち」にこだわり、訴訟、紛争に強い弁護士と関係を持ちたい
そんなお考えを持ったことはありませんか。
特に、相談相手もいなければ、自らの意思決定を批判してくれる人もいない中小企業の経営者は、そう思いつつ、そのまま先送りしておられませんか。
Contents
顧問契約を結び継続的に法律相談等の法律事務の提供をすることを約束している弁護士である、といわれます。
しかし、そのような一般的・抽象的説明ではイメージがわきません。
実際、経営者・管理者の方々からは、次のような声が聞かれます。
・「顧問弁護士が欲しいが、誰に頼んだらよいか分からない。」
・「顧問弁護士は、何を、どこまでしてくれるのか分からない。」
・「顧問弁護士に関心はあるが、依頼するのには、今ひとつ踏ん切りがつかない。」
また、次のような声も聞かれます。
・今の顧問弁護士に不満を感じている
・現在の弁護士の対応方針とは異なる意見が欲しい
・専門性のある弁護士の意見が欲しい
・訴訟、紛争に強い弁護士との契約を検討している
顧問弁護士の役割は、医師に喩えられ、次のように説明されることが多いです。
医療の分野に、病気を予防する予防医学と発生した病気を治療する臨床医学とがあるが、法律の世界にも、予防法務と臨床法務がある。
顧問弁護士は、経営者の「かかりつけ医」であり、その役割は、トラブル・紛争を未然に防ぐこと、万が一トラブル・紛争が発生した場合に迅速に対応し、訴訟に持ち込まずに、早期解決を図ることにある、と。
しかし、企業法務において、トラブル・紛争の「予防・早期解決」は、徹底追求すべき目的ではありますが、それはあくまで理念的な原則論です。
もし早期解決の実態が、相手方との拙速な妥協でしかないのであれば、かえって将来に火種を残し、円滑な企業経営を阻害するものともなりかねません。
実際、当事務所では、1330万円余りの未払残業代等を請求された事件で、会社側の代理人として475万円で和解を成立させた事例や、最高裁判所まで持ち込んで、独りよがりな高裁判決を破棄してもらった事例もあります。また、私が顧問弁護士に就任する前にされた安易な妥協が災いして、北海道労働委員会では、埒が明かず、東京の中央労働委員会まで赴いて勝訴的和解を成立させた事例もあります。
弁護士広告が原則自由化され、インターネットが普及した現在では、“弁護士大量増員時代”の到来も反映してか、弁護士の側から、「紛争化する前の予防」であるとか、「スピーディな解決」といった表現を用いた宣伝が多くされるようになっています。
しかし、「訴訟に持ち込まない解決」の中身が、“弁護士の訴訟スキル・ノウハウ不足”を覆い隠すものであったり、「処理のスピード化」が、早期の報酬確保といった“事務所経営の効率化”のための方策にすぎないのであれば、本末転倒というほかありません。
そもそも、実効的な「予防法務」は、訴訟で場数を踏んだ上での経験を基に構築できるものです。経験不足が否めない未熟な弁護士が、机上の空論でどこまで予防できるのかは甚だ疑問といわざるを得ません。
顧問弁護士の選び方として、次のようなポイントが挙げられるのが一般です。
1)企業法務に関する知識・経験が十分
2)レスポンス(回答)が早く、対応・処理がスピーディ
3)親身で、説明が分かりやすい。
4)トラブル対応だけでなく、情報提供や提案をしてくれる。
しかし、そうは言っても、医者と違って、決して身近とはいえない弁護士との付き合いは、ほとんどイメージが湧かないとうのが実際だと思います。
実力不足の弁護士は問題外ではあるとしても、実力は、実際に何かをしてもらわないと分からないというのが現実です(実は、医者の場合も同様ですね。)。
ですから、弁護士選びに迷ったら、信頼のおける人からの紹介が一番ということになるのかもしれませんが、それは、成功の確率が高くなるというだけで、最後は、ご自身で決める必要があります。
しかし、経営者としては、徹底的に闘わなければ解決できない場面や状況がたくさんあります。
もちろん、争いばかりを好むのは論外ですが、「早期解決」という魅力的な言葉に飛びついて急いで妥協し、問題をきちんと解決せずに終わり、将来のトラブルの原因を残すことがよくあります。
一方、経営者が徹底して闘うと決断したのに、〝和を以て貴しとなす〟という信条で、〝無難にまとめよう〟とする弁護士では、相手に押されてしまい、劣勢に立たされることにもなりかねません。
特に、「早期解決」がただの表面的なもので、実際は弁護士のスキル不足や報酬のために選ばれる方策であれば、本末転倒と言えるでしょう。問題を最良の方法で解決するためには、企業の実態や実情に加え、企業独自の志向、そして経営者のキャラクターやパーソナリティーも踏まえで、依頼者と弁護士が「協働」できる関係が不可欠です。
法的な紛争を解決したり予防したりする経営者は、まず、まず、弁護士からの説明を通じて自分の立場を客観的かつ具体的に理解し、適切な解決方法を見つけることが重要です。
そのためには、弁護士とのコミュニケーションが十分となることが大切です。弁護士との相性は、会社の状況やビジネスの性質、経営者自身の個性によって影響され、紛争の解決方法に影響を与えます。弁護士の実力も重要ですが、「相性」も考慮すべきポイントです。
もちろん、話をしっかり聞いてくれる弁護士は良いですが、ただ愚痴を聞いてもらったり、同情してもらうためだけではなく、クライアントの状況を理解し、具体的な解決策を提案することが弁護士の役割です。
法律問題なのかどうかの判断さえが難しいことがあります。相談することで、法的なリスクや問題の本質を理解できます。時には予期しなかった問題が浮上することもあります。日常から顧問弁護士との関係を築いて、いつでも相談できる環境を整えることが大切です。

ところで、フレデリック・W・テイラーをご存じでしょうか。
テイラーは、製造業における肉体労働の生産性を50倍に向上させる「科学的管理法」を完成させ、先進国経済を生み出したと紹介されている技師・エンジニアで経営学者です。「マネジメントの父」と呼ばれ、「顧客創造」という言葉で有名な経営思想家ピーター・F・ドラッカーの著書の中にしばしば登場する人物です。
テイラーの手法は、初めに仕事を個々の動作に細分化し、その動作に要する時間を記録します。無駄な動作を探し、不可欠な動作を短い時間で簡単に行えるように、それらの動作を組み立て直すのです。そして、最後の仕上げに、各動作に必要な最適の道具を作り直す……。
それが、一体、弁護士の業務、活動とどのような関係があるのか。
このテイラーの手法が全米に広まったのは、アメリカ東部の鉄道会社が、貨物輸送運賃の値上げを要求した事件がきっかけとするものでした。
荷主側の弁護士ルイス・ブランデーズ氏が、テイラー管理法を紹介し、鉄道会社の非効率な運営を指摘して、運賃の値上げ要求を撤回させたのです。
単に法律論を展開するのではなく、経営管理の実態にまで踏み込んだ論戦によって依頼者の利益を確保したのです。
このようなことは、極めて稀なことかもしれません(もっとも、当方の提案内容が、相手方にとってもメリット、ベネフィットがあることを提示することは、常に、解決のために有力な手法です。そして、弁護士には、これを相手方に伝達できるスキルが必要です。)。
しかし、顧問弁護士という立場は、法律論ばかりではなく、顧問先企業との間で、深い関係を構築しながら、法律紛争の解決、予防において顧問先企業の置かれた立場を客観的に観察し、企業独自固有の志向に合わせて個別具体的なサービスを提供させていく必要があります。
事案によっては、他のプロフェッショナル、例えば、税理士先生ら他士業の先生と組むことがあります。
次の先生とは、宗教法人を依頼者に、教会に適切な物件を競売で取得して、従来からの賃借人との交渉で調整を図るとともに、不動産取得税に対する対策を目論み、「法律」と「税務」の協働で成果を実現しました。この先生とは、賃料不払を起こした賃借人を物件から排除し、次の買い人に売却するというプロセスを協働実現するなどしました。そのたび、世間では知られていないであろうノウハウを山のように仕入れることができました。
〇税理士・男性(73歳・男性)
前田先生には、多々御世話になっております。この度、先生に依頼した事業等について、色々な想いがありますが、その感想はと云われますと、私としては次のような点が示されるのではないでしょうか。
私たち税理士も当然、税法という法律に基づく職務としている訳ですが、仕事柄、お得意様からは様々な相談も多く、税法に関することはもとより、一般的な法律については解決が可能であるが、係争に発展しそうな案件については、やはり専門知識人でなければならない場合も数多くあります。その為、大切なお得意様から弁護士先生を紹介して欲しいと、依頼されることも多い訳です。法律事務所に頼んだら、どの程度の期間・費用がかかるか、更には結果はどの程度、依頼者の希望を満たしてくれるものなのか!!期待と不安が多いように感じられます。
そこで、私が前田弁護士を推薦させて戴いている要素は、次の点にあります。
1.依頼者の意思と事実関係を的確にとらえること
依頼者の多くは、自己が100%に近い有利性を主張する事が多いが、事案の事実関係の経過等を適切かつ正確にとらえ、係争するに当たってのメリット・デメリットを検察し、依頼者との連携を計っている。
2.依頼者の心をとらえ、適正な方法を導き出し協力を促す
3.動き出したら迅速に処理に向かう
依頼者からみると、いつ手がけ、いつになったら結果が出るかを期待しているものです。先生は経験上、XX日頃 このようなこととなり、XX日頃はこの様な事実確認等あり、XX日過ぎ頃このようなこととなる・・・と、具体的にその進行状況の報告が行われている。
4.案件によって、より有効な資料等の検索が速い
依頼者の100%期待通りとならないにしても、相手のウイークポイント等の確認等が速く鋭い。
同じ売掛金の回収にしても、相手に対する内容検索により的確な処置によって全額貸倒になるか、一部でも回収出来るかは大変は違いで、その方法・手段は最も優れている。
5.的確なアドバイスと信頼性
係争等の場合は、時間との勝負でもあると思われる。このようなことから、適切なアドバイスに相互間の信頼と強調を確立する指導力に長けている。
6.その他
弁護士費用、いわゆる報酬であるが、事件引き受けが決まる時点で、アバウトの金額が掲示されるので、依頼者も安心である。
以上が、私の前田弁護士に対する感想ですが、彼は人間的触れ合いを大切にされる方で、お客様の多くは、率直な性格を快く受け入れておられると思います。

自分にとっての良い弁護士を探すのは、最高の治療を受けるために名医を探すのと同じです。とにかく会ってみないとわかりませんし、その際、ピンと来なければ依頼しなければいいだけのことです。
愛想が良く、しっかり話を聞いてくれる医師がやぶ医者だったり、この世にただ一人と確信して結婚したのに、すぐに離婚、という話をよく耳にします。弁護士選びも同様で、良さそうな人選び、ダメなら辞めさせればよいだけのことです。
弁護士にも、“当たり・外れ”があるわけですが、自分にとって、相性が合い、きちんとコミュニケーションをとれる相手であるかどうかが重要になるでしょう。
弁護士は、法律の話に終始せず、依頼者が置かれた状況をきちんと理解し、トラブルの個性や特殊性を具体的に把握しなければならない。その上で今後どのような手を打ち、解決に向けた舵取りをするのが適切かを依頼者にきちんと説明しなければならない。人間関係の原点のような部分が何より優先事項です。
私は、依頼者にとっての「勝ち負け」は何なのかにこだわります。実は、勝ち負けの理解は、すべての人にとって同じではありません。経営者のキャラクター・パーソナリティーは様々であり、依頼者と弁護士はこのことを突き詰めなければならないのです。
そして、紛争解決・紛争予防のモデルは「訴訟」にあり、実践的に「訴訟」で有利に活動できるスキルとマインドこそが、弁護士に必須の基本的能力であると考えます。
訴えを提起する場合には、勝たなければなりませんし、訴えを提起された場合には、負けるわけにはいきません。また、訴訟外で解決を図ろうとする場合、あるいは紛争予防の措置を取る場合であっても、百戦錬磨の「訴訟」経験で裏付けられた実践的なスキル、マインドが欠かせません。
最終的な解決機関である裁判所に持ち込まれた場合を想定しておかなければ、将来にわたっての対応としては不十分なのです。
私は、これまで様々な種類の訴訟に関わり、顧問弁護士として常時30以上の企業を直接にサポートしてきました。30年を超える弁護士経験と豊富な実績があります。この経験と実績に基づいた強みを活かし、依頼先企業の状況や志向、経営者の個性などを考慮しつつ、紛争の予防や解決に取り組んでいます。
以下の点を特徴としています。
・訴訟、紛争対応の経験実績が豊富(企業法務に関する[解決実例・実績])
・顧問先企業の事案は全て代表が直接担当
・経営課題を踏まえ、個別の状況を鑑みた対応が可能
・チャット、Zoomなどコミュニケーションツールが柔軟
・3万円から顧問契約が可能
・顧問弁護士の外部表示(HP、会社案内、名刺、パンフレットなど)が可能(詳細はこちらをクリックしてください)
「顧問弁護士」・「企業法務」についての関心をお持ちの方は、是非、ご連絡ください。
私が、貴殿と相性が合い、コミュニケーションがとれる相手であるかどうかをご自身の目で確かめるつもりで一度ご来所いただけますと、幸いです。
当事務所で取り組んで来た対応をご理解いただくために、[お客さまの声]をいくつかご紹介いたします。
互信ホールディングス株式会社
代表取締役社長 平島 誉久 様
[主要子会社:明星自動車(株)、札幌日交タクシー(株)、タクシーネクスト(株)、昭和ハイヤー(株)、三和ハイヤー(株)、夕張第一交通(株)、互信自工(株)、札幌三起(株)]
梅野産業株式会社
代表取締役 梅野 隆 様
株式会社 駿河
代表取締役 大井 祐子 様
[賃貸事業部主要店舗:アパマンショップ千歳店・恵庭店・苫小牧店・苫小牧中央店]
〇広告会社管理者・男性・36歳
今から数年前、ある日の札幌市内の居酒屋でした。
その時奥様と見えられていた、人の良さそうなルネッサーンス髭男爵さん(すみません!)の隣に、小生がたまたま隣り合わせ、その場で意気投合させていただいたことが、前田先生を存じ上げる始まりでした。
小生は、販売促進担当として、会社の売上や客数に関わる生命線を企画・実施する業務のため、職務柄幅の広い各取引先や同業他社も含め経営トップや幹部の方々とのコミュニケーションをはかる機会も多く、日々の営業活動における様々のご相談をお受けする事も多くございます。そんな時、専門的なお話の場合にご相談・ご紹介申し上げるのが前田先生です。
私にとって大切な方をご紹介する上で欠かせない、依頼者の身になってお考えいただく姿勢と、ざっくばらんなお人柄に、とても有難く感謝致しております。
信頼のおける医者とファイナンシャルプランナー、そして弁護士の先生は、豊かな人生を送るための個人的に必須のパートナーであると言いますが、今本当に実感致しております。
前田先生、今後とも末永くご指導下さいます様、心よりお願い申し上げます。
そして、「相性」が合えば、次のような発展的関係を築いていくことができます。
〇農産物販売会社代表者・男性・47歳
結論から言いますと、今後の私の人生が大きく変わりました。先生のご意見、考え方を吸収し、仕事に人生観に大きな自信を希望を与えられました。
依頼に関しては、すべての事柄がはじめてのものですから、感想と言えるかわかりませんが、振り返って思い出すと、先生との打ち合わせ後に、なるほどとか、こんな考え方、こんなやり方と思い、満足している私がいました。また、一つの事柄にも色々な角度から考え、深く考えるようになりました。活字や言葉では表現できない感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。今後も見捨てずによろしくお願いします。
文章が下手なものですから「依頼しての感想」には少し的をはずれているような気がしますが、お許しください。
また、次のような濃い協働関係が確立できます。
〇リース会社・会社役員(その後代表取締役)・男性・50代
前田先生には、いつも御世話になっております。
弊社は顧問契約の基、様々な法務的相談を頂いており、その回答も的確にご指示を下さり、即行動をする案件では当然、後ろ盾の先生がいる事で、安心感が増して行動に挑めます。時には弊社の主張をし、引く事で損失が軽減される案件もあり、都度環境に合った指示及び助言を受けることで、最終判断・・・つまり社長決済に必要な事前検討が整う状態に弊社はなりました。加えて、それらの相談時には関係・関連する法令等のご説明もして頂き、スキルアップにも繋がっております。
また、幹部社員及び営業部門社員に初歩的な法務講演会を開催下さり、弊社では定期開催をする予定にさせて頂いております。先生のお力を借り、一歩ずつ弊社社員の能力向上も期待しつつ、「共同」で会社成長を望んでおります。
並びに個人的感想ですが・・・辛いこと大変なこと程、過ぎてしまうと良い思い出になります。又、乗り越える事で冷静な判断力及びスピーディな行動が生まれてくると、信じております。決して辛いことばかりでは有りません。会社人生も私的な人生も必ず良い事は巡ってくるもので、巡る為に歩む努力を諦めないことと思っております。
暗闇や嵐の中での一光の「灯台」として、前田尚一法律事務所を、弊社はパートナーとして共に歩んで行こうと思います。
〇 土地区画整理組合副理事長・男性・75歳
私はまったく素人でしたが、知人からの要請で土地区画整理組合の役員に選出されましたが、この時、組合の専務理事(組合でただ1人の常勤者)に選出され、実務の中心となっていたA氏が就任一年半後にB建設業者との間で「贈収賄事件」(H7.6.20)が生じ、H氏に有罪判決が出されました(判決前にH氏は理事を辞任)。又、同年の4月初め頃にA氏が別なC建設業者と話し合う中で(事前に理事会への提案や承認がない中で)勝手に工事の発注を行い、同年7月上旬にB業者より、工事代金が水増しして請求された事が明らかとなり「工事代詐欺未遂事件」が発生しました。
その後も組合とA氏の間で「養豚業廃業補償費増額請求事件」(道収用委員会~最高裁まで)や、「豚舎明け渡し請求」「自宅撤去、土地明け渡し」及び同左の「強制執行請求」等、数件の裁判がそれぞれ合わせて約5年にわたり行われました。
それまで組合としては、話し合いでの解決を求め、根気よく年時をかけてきましたが、このままでは解決の目処もたたず、事業も進まず、止まることも考えられる状況となってきましたので裁判での解決を求めていかざるを得なくなりましたが、組合員や行政等から裁判にかければ判決まで多年を要するし、お金もかかるのではないかと心配や反対の意見もそれなりにありましたが、組合としては、先生との相談、話し合いの中で、解決しない話し合いをいつまで続けても意味がないし、又、ゴネ得を1人許せばそれを見て他に色々と言ってくる人が何人かは出てくるのでないか(現実にその可能性は何人か考えられました)、それであれば裁判に堂々として臨んだ方が早く解決し、又お金もかからないのでないか等、原則的な考え方が示される中で、当初は100%理解できた訳ではないが、私達の考えや気持ちにふれるものが多く、先生を信頼してお願いし、一緒に戦っていってみようという気持ちを強くしました。
幾つもの裁判を通じて理解した事は色々とありましたが、私なりに要約すると、
1 先ず先生を信頼する事、そして依頼人としての考えや気持ち(求めている事)を素直に伝える事
2 先生の、その裁判に当たっての考え方、取り組み方等を素直に受け止め、解らないところは恥ずかしがらずに聞き、ひとりよがりの判断や考え、早合点しない事
3 裁判に対する対応は、ぶれずに一貫してプロである先生に一任し、自分たちもそれに素直に対応していく事
4 周りからの色々な考えや意見については素直に受け止めるが、それらの事で先生との間で不信やぶれが生じないよう、必要に応じて先生との相談・話し合いを密にしていく事、
が、裁判に臨み、共に戦っていく上で、大事ではないかと思っています。
未経験な裁判と言う大事な問題で、根気強く何かとお話をして下さり、最後まで先にたって戦い、又、引っ張っていただき、何とか私達もついて行き、幾つも勝ち得た事は本党に有難く感謝しています。
先生の努力とご苦労はいつまでも忘れません。
私達も良い経験をさせて頂きました。
〇「企業法務」に関する
[解決実例・実績]
弁護士前田尚一の【公式サイト】はこちら
