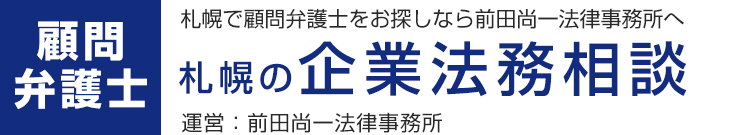

紛争が発生し、訴訟を提起された場合はもちろん、訴えを提起しなければ、解決が難しいという場合には、「企業にとっての勝ちは何か」を徹底して考え、最善の対応方法を考えていかなければなりません。紛争の解決を図る方法は、紛争それ自体の性質ばかりでなく、企業の事業・業態の内容、実情はもちろん、経営者個人のキャラクター・パーソナリティーによっても大きく左右されます。
Contents
企業法務においては,トラブル・紛争を未然に防ぐこと,万が一トラブル・紛争が発生した場合に迅速に対応し,訴訟に持ち込まずに,早期解決を図ることにあると,言われます。
それはそれでそのとおりで,企業法務において,トラブル・紛争の「予防・早期解決」は,徹底追求すべき目的です。
しかし、徹底して闘わなければ解決できない局面が多々あります。
早期解決の実態が,相手方との拙速な妥協でしかないのであれば,かえって将来に火種を残し,円滑な企業経営を阻害するものともなりかねません。
弁護士広告が原則自由化され,インターネットが普及した現在,“弁護士大量増員時代”の到来も反映してか,弁護士の側から,「紛争化する前の予防」であるとか,「スピーディな解決」といったことが強調される傾向が強くなってきています。
「訴訟に持ち込まない解決」の中身が,“弁護士の訴訟スキル・ノウハウ不足”を覆い隠すものであったり,「処理のスピード化」が,早期の報酬確保といった“事務所経営の効率化”のための方策にすぎないのであれば,本末転倒というほかありません。
著名な裁判官経験者によると,次のとおり,企業同士が原・被告となる訴訟が増えてきており、企業間での紛争を司法の場で決着つけようとする姿勢が顕著になってきたとのことです。
「これまでの企業関係訴訟では企業が被告となる事件が多かったが,平成10年前後から,徐々に企業同士が原・被告となる訴訟が増えてきた。これが,企業間訴訟であり,企業間取引をめぐる紛争は企業活動の死活問題となることさえある。こした状況の下,企業においても,企業間取引紛争を司法の場で決着をつけようとする姿勢が顕著になっており,この傾向は,大都市圏から地方都市部までに及んでいる。」(加藤新太郎『企業間取引訴訟』)
こうした動きは、これからますます加速すると予測されます。
社会全体について見ると、ビッグバン、規制緩和が大きく実現した現在、個々の事案について行政の設定するルールの力は弱まっています。入口での事前規制がされないのであれば、紛争が起きるのは当然です。真に譲れない場面では出口である「司法」で事後的にチェックされるという構造になるでしょう。
もっとも,中小企業の場合、取り引き先の大企業を相手に物申せば、仕事がもらえなくなるといった心配があります。
実際,これまでは,理不尽な場面でも泣き寝入りすることが多かったのではないでしょうか。企業間訴訟の現状は、まだ大きな企業同士のケースが多いと推察されます。
しかしながら、大量生産、大量消費の時代は終わり、社会は地殻変動を起こしています。企業は売上至上主義では生き残っていけないのが現実です。
特に中小企業は自社の独自性を基に必要なものを見極め、ピンポイントで活動していかなければ、存続は難しいでしょう。
そして,中小企業の公正な取り引き環境の実現を目指し、下請け取り引きの適正化が現代の潮流になりつつあります。
つまり、トラブル・紛争に対してどのような姿勢をとるのか、将来を見据えた上で、確固たる意思を持って決断する場面が増えてくるということです。
訴訟提起がより身近なものとなり、現実的選択肢になってきます。
弁護士も企業に対し、型どおりのサービスを提供しても存在意義はありません。
個々の企業と手と手を取り合う深い関係を構築しながら、それぞれの志向に合わせて個別具体的なサービスを提供する必要があります。発展途上である現在のAIでは対応できないであろうマインドやスキルが肝です。
当事務所では場数で培った経験と訴訟のマインド・スキルを活用し、例えば元請会社に訴訟を提起すべきかどうか、弁護士として有益・有用なアドバイスをしていきます。
紛争解決を裁判所に持ち込まれた場合、一方当事者としては、勝つためのポイントを把握して、訴訟における審理手続と運営の枠組みの中で、有効な訴訟活動を的確かつ効率的に行わなければなりません。
その場合、その訴訟を現に審理・判断する裁判官を説得することができるかどうかが決め手となります
目の前の裁判官を説得するための訴訟活動を展開していくには、専門知識に加え経験・実績に基づいた訴訟技術が不可欠です。訴訟の内容が複雑であったり、高額な請求を行うような訴訟の場合、弁護士に依頼せずに民事訴訟を進めることは困難です。
紛争に巻き込まれた経営者にとって重要なことは、依頼する弁護士からの説明を通じて、まず自身の状況を客観的に理解し、適切な解決策を追求することです 企業間紛争を解決するに当たって、争いばかりを好むことが適切とはいえないとしても、紛争をうやむやにせずに徹底して闘わなければならないことが多々あります。
しかし、そのような状況でも、「早期解決」という言葉に飛びつき、拙速に妥協してしまい、問題を完全に解決せずに将来のトラブルの種を残すことはよくあります。
そして、経営者が徹底して闘うと決意した場合に、弁護士が「和を以て貴しとなす」という信念のもと、「無難にまとめよう」とする姿勢を取ると、相手に一方的に押され、立場が弱くなってしまうこととなりかねません。
こうした点を考慮する場合、信頼できる人物を紹介してもらうのが最も良い方法ですが、いずれにしても、実際に会ってコミュニケーションをとれる相手であることが重要です。つまり、「相性」が重要なポイントとなります。
とにかく会ってみないと判断できません。ピンと来なければ依頼しなければいいだけのことです。
私は、依頼者にとっての「勝利」とは何かにこだわっています。
また、紛争解決のモデルは「訴訟」であり、実際に「訴訟」を行うスキルとマインドが、弁護士に必要な基本的な能力だと考えています。
これまで、さまざまな訴訟に取り組みながら、中小企業の「企業法務」全般に注力し、常に30社以上の企業を顧問弁護士として直接担当し、30年以上の弁護士としての経験と実績を積んできました。
この経験と実績を活かし、依頼先企業の実態や事情に加えて、企業独自の志向や経営者のキャラクターやパーソナリティも考慮し、紛争の予防と解決に取り組んでいます。
ご興味があれば、お気軽にご相談ください。
なお、ここで,当事務所で担当した,企業法務に関連する民事訴訟をご紹介いたします。
個人情報・プライバシーの問題がありますので、判例集、判例雑誌に登載され、または、新聞等マスコミで報道されるなど、一般に公表された案件のみをご紹介いたします。なお,事件ごとの詳しい内容は,別稿で解説してあります。
家業を法人化した際、先代が株式払込金を支出した場合において、長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため、その株式払込義務を代わって履行したものであるとして、長男・長女の株主権を認めた事例
(経営者にタッチしていなかった少数株主側を代理)
札幌地方裁判所平成9年11月6日判決
・会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例
(交通事故被害者である会社代表者(死亡)の遺族を代理)
札幌地方裁判所平成9年1月10日判決
・交通事故で死亡した57歳の小規模な会社代表者の逸失利益について、役員報酬年額840万円全額を労務対価部分とし、70歳まで稼働可能として算出された事例
(交通事故被害者である会社代表者(死亡)の遺族を代理)
札幌地方裁判所平成21年2月26日判決
・施設入所者に対する虐待行為が行われている旨の記事が新聞に掲載されたことに関し、複数の目撃供述等が存在することを認識していたものの、他の事情から虐待行為はなかったとして、同施設を設置経営する法人が新聞への情報提供者である職員らに対してした損害賠償請求訴訟の提起が違法な行為とはいえないとされた事例
(社会福祉法人・特養ホームを代理)
最高裁判所平成21年10月23日第二小法廷判決
・北海道の住民である原告らが、北海道A支庁における農業土木工事において談合が行われていたとして、同工事の受注をした2会社と同工事の請負契約締結当時の北海道知事、北海道A支庁長及び北海道農政部長に対し、地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき、北海道(参加人)に代位して、損害の賠償を求めた事例
(建設業者を代理)
札幌地方裁判所平成19年1月19日判決
・商品取引業者の外務員らの商品先物取引の勧誘に適合性原則の違反があったとして商品取引業者の不法行為責任を認めたが、5割の過失相殺を認めた事例(商品先物取引業者を代理)
札幌地方裁判所平成20年2月26日判決
・公益法人から除名処分を受けた会員の仮の地位を定める仮処分申立てについて、被保全権利の疎明がないとして却下された事例
(公益法人を代理)
札幌地方裁判所平成11年1月26日決定
仮換地指定がなされた従前地について、施行者の管理権に基づく妨害排除請求を認めた事例
(土地区画整理組合を代理)
札幌地方裁判所平成9年6月26日判決、札幌高等裁判所平成9年10月31日判決
・「「円山葬儀場」訴訟外で決着 反対派が業者へ建設断念和解金 9800万円」
(宗教法人をメンバーとする住民側を代理)
読売新聞平成7年2月16日朝刊その他の日刊紙、TVニュース