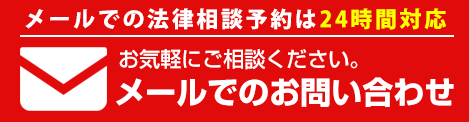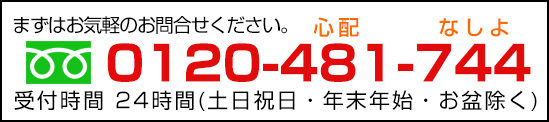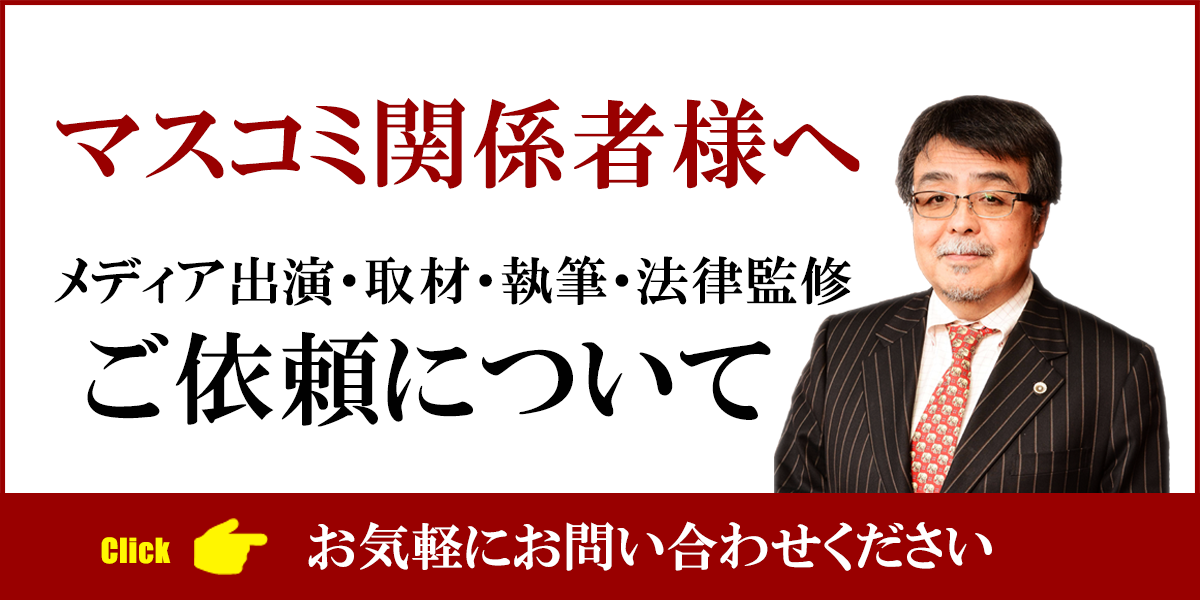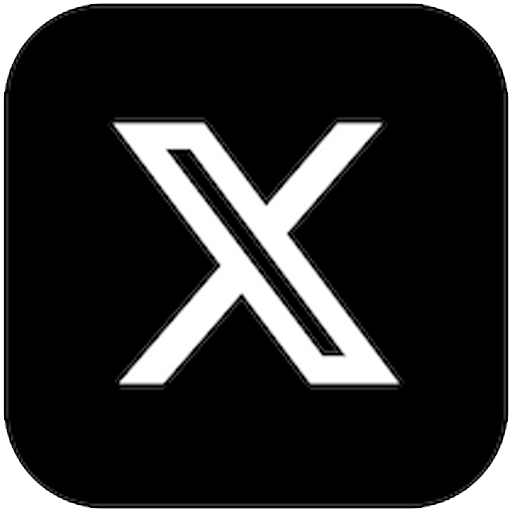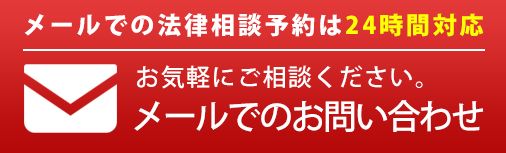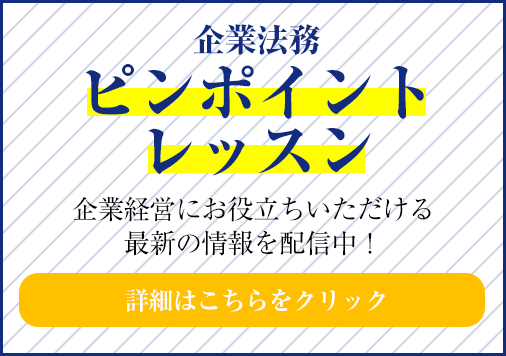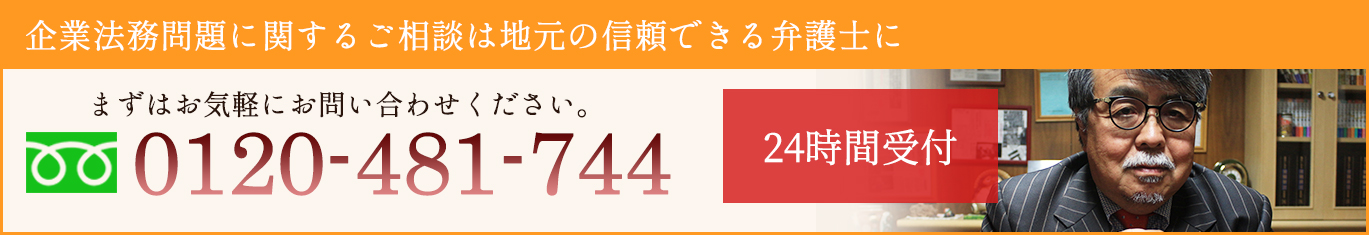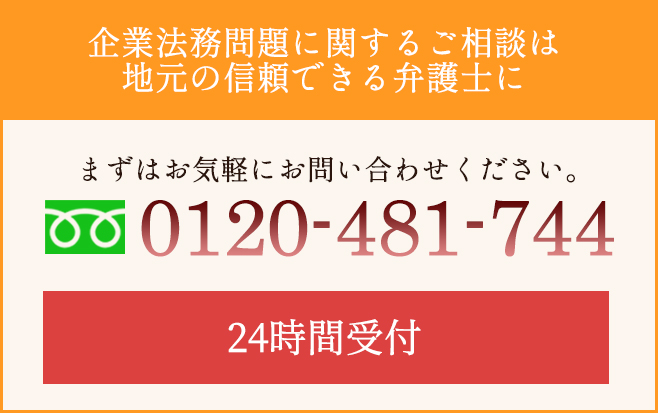Contents
躊躇する裁判官の背中を押す:土地区画整理事業の事例
・仮換地指定がなされた従前地について、施行者にその不法占有者に対する明渡しが認められた事例
札幌地裁平成9年6月26日判決
札幌高裁平成9年10月31日判決
「組合区画整理」59号32頁
顧問先の土地区画整理組合から依頼されて訴訟追行した裁判例です。
本件は、この裁判例(前件)に続いて起きた同一当事者間の案件(札幌地裁所平成9年(ワ)第1672号同10年4月28日判決)を紹介します。
前件、本件いずれも、土地区画整理事業において、不法占有者に対する土地明渡しを求めた事案です。
土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業であり、土地の区画形質の変更にあたり、従前の土地に代えて換地を指定し、従前の土地(「従前地」)上の権利関係に変動を加えることなく換地上移行させる「換地処分」が行われます。そして、事実上換地処分がされたと同様の扱いをする「仮換地の指定」という制度が設けられています。
仮換地の指定がされると、従前の土地の所有者その他の権利者は、原則として仮換地につき、従前の土地におけると同様の使用収益をすることができる反面、従前の土地については使用収益することができないものとされています。つまり、A土地(従前地)の代わりの土地としてとりあえずB土地(仮換地)が指定されると、Aの土地の所有者は、A土地の使用収益が停止さます。
最高裁は、土地区画整理法100条の2の規定により従前の宅地を管理する施行者は、所有権に準ずる一種の物権的支配権に基づき、正当な権原なく同宅地を占有する者に対し、その明渡しを請求することができる、としています(最高裁昭和58年10月28日第二小法廷判決)。先行事例はこの判例にのっとったものです。
しかし、本件の担当裁判官は、裁判官は、土地区画整理組合法100条の2の見出しが「(仮換地に指定されない土地の管理)」であることにこだわり、この判例に従った判断をすることに躊躇し続け、当方で実態を法律論として構成して提示しても、議論は平行線のままでした。
同じく状況とはいえ、判例は「公共施設予定地」の事案であり、先行事例は、「留地等予定地」の事案だったのに対し、本件は、別の従前地の仮換地として指定を受けながら、使用収益開始日が定められていない(「追而指定」)という事案でした。係争地(従前地)は、の仮換地として指定を受けながら、使用収益開始日が定められていない(「追而指定」)という事案でした。
ところが、当方で、建設省都市局区画整理課が、専門雑誌の中で、本件のよう場合にも土地区画整理組合法100条の2が適用されると説明している解説(「質疑欄 仮換地指定及び使用収益の停止の効果について」『組合区画整理』14号)を見付け、これを証拠として提出した途端、一気に裁判官の態度が変わりました。
そして、「仮換地指定処分がなされた従前地にあたる係争地ついて、この係争地を仮換地とする指定が別途なされたが使用又は収益を開始することができる日が未だ定めらていない場合、土地区画整理法100条の2により、換地処分がなされるまでの間、施行者が管理するものとなるとして、…………」とそれが当然の帰結であるかのごとくの当方全面勝訴の判決が言い渡されました。
判決書の中に、それまでの議論がされた内容は、争点としてどころか、全く触れられておらず、証拠として提出した文献も挙げられていません。
審理過程において判決までの裁判官を観察していると、意図的というべきかどうかはともかく、裁判官の結論を導いたプロセスと、判決書で述べられる理路整然とした理由説明とが一致しないことがままあります。
本件においても、判決書だけを見る限りは、そんなこと初めから分かっていたよというノリですが、裁判官が証拠として判決書の中に証拠として明記することをはばかることもあります。しかし、小道具であっても、その効果は抜群という場合があることも事実です。本件の場合は、足元を固める権威付けを当方で提示し、裁判官の躊躇を取り払う後押しをしたことになるでしょう。
前田尚一法律事務所の取組
私は、依頼者にとっての「勝利」とは何かにこだわっています。
また、紛争解決のモデルは「訴訟」であり、実際に「訴訟」を行うスキルとマインドが、弁護士に必要な基本的な能力だと考えています。
これまで、さまざまな訴訟に取り組みながら、中小企業の「企業法務」全般に注力し、常に30社以上の企業を顧問弁護士として直接担当し、30年以上の弁護士としての経験と実績を積んできました。
この経験と実績を活かし、依頼先企業の実態や事情に加えて、企業独自の志向や経営者のキャラクターやパーソナリティも考慮し、紛争の予防と解決に取り組んでいます。
ご興味があれば、お気軽にご相談ください。
[ご参考]
Contents [hide]
- 1 企業間紛争について民事訴訟の活用場面:特に中小企業の場合を念頭に
- 2 企業間紛争を民事訴訟で解決するメリットとデメリット
- 3 民事訴訟で「勝つ」ために
- 4 当事務所の取扱事例からエピソードをいくつか
- (1)事案の特殊性を明らかにし、裁判実務上の取扱いの例外として扱われるべき事例であることを説得すること:オーナー社長の死亡に対する対処の事例
- (2)躊躇する裁判官の背中を押す:土地区画整理事業の事例
- (3)裁判官の判断は、その個人的な視野・価値観の外にはでない(勝訴判決が判例雑誌に掲載される前に、逆転判決が出て狼狽えたこと):ゴルフ会員契約の解除の事例
- (4)裁判官が判決の理由を書きやすい主張を構成する:会社の支配権の確保の事例
- (5)事件ごとにそのたび、そのたび繰り返さなければならない:オーナー社長の死亡に対する対処、再び
- (6)裁判例の相場どおりにせずに、認容額を増額させたり[原告事案]、割合を下げて支払額を減額する[被告事案]:名誉毀損の事例、商品取引の事例、官製談合の事例
- 5 弁護士の選び方
- 6 前田尚一法律事務所の取組